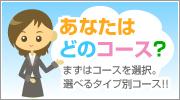濃縮!社会福祉士 無料!過去問特集
「過去問特集」コーナーでは、社会福祉士試験で過去に出題された試験問題と解答を掲載しています。過去問は自分の実力を試す際に、チャレンジすることもできますが、それ以上に「学習をこれから始める!」といった時期に活用するのが非常に効果的です。過去問を見れば、試験の傾向をつかむことができます。社会福祉士の学習を、これから始めようとしている方も、ぜひ一度、過去問を解いてください!
第25回過去問題
相談援助の理論と方法③
専門科目
第112問
事例を読んで, D相談員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち,この段階における対応で,より適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
U市の児童福祉課のD相談員に,子育て支援センターの保育士から,育児不安気味の母親が相談を希望しているという連絡が入った。D相談員はすぐに自宅に出向き, Eさん(33歳)が長男(2か月)を出産後,うつ状態で,外出もあまりできないこと,近くに頼れる人がいないこと,夫は仕事が多忙で育児に協力的でないことなどの話を聞いて,援助が必要と判断した。。相談員はすぐにネットワーク会議を聞き,市保健センター保健師,子育て支援センター保育士,主任児童委員を集めて,援助方針を協議し,各々の役割分担を検討した。
1. 市保健センターが行っている乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)を利用して, Eさんとの支援関係を築くようにする。
2. 夫に育児に積極的に参加するよう主任児童委員から促してもらい,定期的な報告を夫に求め,自らも含めた三者で確認する。
3. ネットワーク機関からの情報を自ら一元的に管理し,必要とされる支援も自らが行う。
4. Eさんのニーズを確認しながら,養育支援訪問事業について説明する。
5. 子育てサークルの情報を伝えて参加を促すため,子育て支援センターの職員からEさん宅へパンフレットを郵送させる。
第113問
社会福祉施設内でのケース会議開催の留意点に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1. 緊張感のある会議にするため,司会者やケース提供者による事前の打合せでは,事例の詳細には触れずに,主に時間配分について検討しておく。
2. 施設に所属する職員が集まる貴重な機会なので,時間の制約を設けず,多くのケースについて,できるだけ丁寧に検討できるようにする。
3. 援助内容についての正しい見解を共有することが大切なので,職員聞の意見が分かれた場合は,多数決により民主的に決定する。
4. ケース会議は,援助の向上のみならず,職員教育の意味合いもあることから,終了後は会議内容の要約を参加メンバーで交代して作成し,共有する。
5. 施設や利用者に対する地域の理解を促すために,希望する地域住民にはケース会議の傍聴を認め,啓発活動の機会とする。
第114問
グループワークの作業期における援助者の役割に関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1. プログラム活動を順調に進めていくことが必要な時期であることから,できるだけ具体的な指示を出しながら,グループ全体の力量を高める。
2. サブグループができた場合には,グループ全体の仲間意識の構築やグループ運営に良い影響を与えるかどうかを見極めて対応する。
3. メンバー同士の衝突や摩擦が起こると,グループ活動による効果が得られなくなるので,できるだけ事前に回避するように働きかける。
4. 孤立するメンバーが現れたときには,仲間意識を高めるチャンスとして,そのメンバーに個別にアプローチするよりも,対応はグループの主体性にゆだねる。
5. メンバー同士の交流が深まった時期なので,グループ内の役割分担をいったん解消して,メンバーのグループからの自立を促すように働きかける。
第115問
事例を読んで,児童館のF職員(社会福祉士)によるグループワークの終結期における対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
昨年7月に,児童館で行っている子育て講座をきっかけにメンバー8人の子育てサークルができあがった。児童館は,その後の活動拠点ともなっている。F職員は,サークルの運営について相談に乗るとともに,様々な子育て支援情報の提供を行い,グループワーカーとしてグループ活動に関与してきた。この結果,グループ内での相互作用が高まり,多様な働きかけのなかで得た成果にメンバーは満足し,グループワークは成功したように思えた。しかし,子どもたちの幼稚園入国とともにサークル活動も終了する段階になると,メンバーの何人かが, F職員に子どもの養育などについての不安を個別に表明してきた。
1. グループのリーダーに終結に向けた取組を任せる。
2. 最後の数回のグループ活動では,子育てに関する知識を補完することを目的に子育て講演会を実施する。
3. 活動終了後における自助グループの立ち上げを行い,そこへの参加をメンバー全員に求める。
4. メンバーの不安を解消するため,このグループ活動を延長する。
5. メンバー自身が活動を振り返り,個々の不安をメンバーで共有できる機会を設定する。
第116問
V市社会福祉協議会では,要介護高齢者の在宅での介護を行う主たる家族介護者を対象としたグループワークを実施している。グループに参加した主婦のHさん(55歳)は,介護に協力的でない夫への不満や,自らが介護している義母との関係にストレスを抱えていた。しかし自分のことを他人に話すのは恥ずかしいという気持ちや,こんなことで悩んでいるのは自分だけだという思いもあって,黙っていることが多かった。しかし他のメンバーが自分と同様の悩みや協力してくれない家族の愚痴などを話すのを聞いているうちに,自分自身の状況に対して違った見方でとらえることができ自分の気持ちや状況について,自ら表現して話をすることができるようになった。次のうち, Hさんの変化に見られるようなグループ活動の効果を表すものとして,正しいものを2つ選びなさい。
1. 波長合わせ
2. 観察効果
3. 集団思考
4. 感情転移
5. 普遍化
第117問
J社会福祉士が部下のK社会福祉士に対して行うスーパービジョンに関する次の記述のうち,適切なものを1つ選びなさい。
1. 利用者から, K社会福祉士についての苦情を聴き,すぐにそれを施設管理者に人事考課のための情報提供として伝える。
2. K社会福祉士が,利用者とかかわるのがつらいと話しながら泣いてしまったので,共感を示すために一緒に泣く。
3. K社会福祉士の業務負担や力量,そしてケースの困難度を勘案して,担当ケース数を配慮する。
4. 利用者への支援について, K社会福祉士から逐一報告してもらい,効率的に業務を遂行するために細かく指示を出す。
5. K社会福祉士が利用者の意向を確認していないことがよくあることを指摘し,上司として自分が利用者の意向の確認を行う。
第118問
相談援助における記録に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1. 叙述体による記録では,実践の説明責任を示す根拠となるよう,事実の経過とともに,面接のやりとりを発話どおりに文字化する。
2. 他機関からの報告は,記録の客観性を担保するため,ワーカーの判断を混じえず,かつ内容の取捨選択をせずに逐語体で記述する。
3. ワーカー・クライエント関係を中軸に行われる実践の記録では,事実関係に加えて,ワーカーの判断やその根拠を記述する。
4. 記録は文字情報として残されるので,状況や援助過程を明確に把握・伝達するために図式化は控え,文章で説明する。
5. 記録はクライエントに開示されることがあるため,本人に不愉快な思いをさせないために,本人に不利益な情報は記較しないよう作成する。
解答
第112問 1・4
第113問 4
第114問 2
第115問 5
第116問 2・5
第117問 3
第118問 3
注目の記事
濃縮シリーズ紹介
なんでも百科
社会福祉士とは
- 社会福祉士とは?
- 社会福祉士になるには
- 社会福祉士資格の制度概要
- 社会福祉士の受験資格取得について
- 社会福祉士国家試験合格基準って?
- 社会福祉士のニーズはあるの?
- 社会福祉士の給料ってどのくらい?
- 社会福祉士国家試験の合格率って?
- 社会福祉士の求人状況って?
- 社会福祉士の通信講座って?
- 社会福祉士の通学講座って?
- 社会福祉士って働きながら取得することって可能?
- 社会福祉士になる適性って?
- 社会福祉士の魅力って?
- 社会福祉士の合格発表っていつ?
- 社団法人 日本福祉士会って?
社会福祉士の試験勉強
- 社会福祉士の試験概要って?
- 社会福祉士国家試験出題基準って?
- 人体の構造と機能及び疾病の出題基準(科目別出題基準)
- 心理学理論と心理的支援の出題基準(科目別出題基準)
- 社会理論と社会システムの出題基準(科目別出題基準)
- 現代社会と福祉の出題基準(科目別出題基準)
- 地域福祉の理論と方法の出題基準(科目別出題基準)
- 福祉行財政と福祉計画の出題基準(科目別出題基準)
- 社会保障の出題基準(科目別出題基準)
- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度の出題基準(科目別出題基準)
- 低所得者に対する支援と生活保護制度の出題基準(科目別出題基準)
- 保健医療サービスの出題基準(科目別出題基準)
- 権利擁護と成年後見制度の出題基準(科目別出題基準)
- 社会調査の基礎の出題基準(科目別出題基準)
- 相談援助の基盤と専門職の出題基準(科目別出題基準)
- 相談援助の理論と方法の出題基準(科目別出題基準)
- 福祉サービスの組織と経営の出題基準(科目別出題基準)
- 高齢者に対する支援と介護保険制度の出題基準(科目別出題基準)
- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の出題基準(科目別出題基準)
- 就労支援サービスの出題基準(科目別出題基準)
- 更生保護制度の出題基準(科目別出題基準)