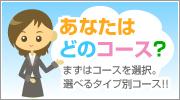濃縮!社会福祉士 無料!過去問特集
「過去問特集」コーナーでは、社会福祉士試験で過去に出題された試験問題と解答を掲載しています。過去問は自分の実力を試す際に、チャレンジすることもできますが、それ以上に「学習をこれから始める!」といった時期に活用するのが非常に効果的です。過去問を見れば、試験の傾向をつかむことができます。社会福祉士の学習を、これから始めようとしている方も、ぜひ一度、過去問を解いてください!
第25回過去問題
相談援助の理論と方法①
専門科目
第98問
ベルタランフィの「一般システム理論」を構成する概念に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1. システムを,有機体としてではなく,機械論的な立場からとらえる。
2. システムを,外部環境に対して聞かれている開放システムとしてとらえる。
3. システムの変容結果は,初期条件によって決定づけられるものと考える。
4. システムを,要素還元主義の立場から,全体は部分の総和であると考える。
5. 個々のシステムを独立したものととらえ,システム間の非階層性を強調する。
第99問
事例を読んで,家族システムの視点に基づいたA社会福祉士の対応に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Bさん(48歳,男性)は,専業主婦の妻(46歳),息子(17歳),娘(14歳)と4人暮らしである。Bさんは,優秀な会社員であり,家族関係も良好であったところがBさんは,半年くらい前から物忘れが増え,仕事のミスが目立ち,病院で検査をした結呆,若年性の認知症であると告げられた。Bさんは自暴自棄になり,妻や2人の子どもに対して当たり散らすなど,家族関係は悪化した。妻から相談を受けた医療ソーシャルワーカーのA社会福祉士は, Bさんとその家族に対応した。
1. 家族間相互のストレスを緩和するために,一時的に別居することを勧めた。
2. 家族システムの開放を目指して,近隣住民にBさんの家族を頻繁に訪問して見守ってもらうように依頼した。
3. 家族関係悪化の原因は, Bさんの荒れた態度だと判断しその改善を図るために,Bさんとの面接を繰り返した。
4. 家族の規範に配鳳しつつ, Bさんの状態に対応して,それぞれの役割を見直すよう家族で話し合うことを促した。
5. 家族内で問題が解決できるように,妻との面接を繰り返した。
第100問
事例を読んで,C社会福祉士による生活モデルに基づいた対応に閲する次の記述のうち,この段階で最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Dさん(59歳)は刑務所での生活が長かった。独身で身寄りはない。出所後のDさんの地域生活の支援は,相談支援事業所のC社会福祉士が担当している。療育手帳の発給を受けた後, Dさんは,現在,中学校時代の同級生が経営する会社で,廃品回収の職に就いている。社長は, Dさんのために,社長命令で若手社員をサポート役として付けた。しかし, Dさんは廃品回収の仕事をなかなか覚えることができず,知らない土地での寮暮らしのため精神的にも不安定になってしまった。DさんとC社会福祉士との信頼関係は構築されており定期的な面接のなかではDさんからの不満も聞いている。そして,最近では,頑固なDさんとサポート役の若手社員との関係も悪くなってきており,社長自身も困惑している。
1. 相手が年下の社員でも,敬語を使い低姿勢で接するようDさんに指導する。
2. Dさんが廃品回収業務で自立できるように,丁寧な技術指導を行う。
3. 新人であるDさんのために,全入寮者による歓迎会開催を社長に提案する。
4. 社長にDさんへの協力を再度求め,関係者による話合いへの同席を依頼する。
5. 地元の自治会長にDさんを紹介して,地域活動への参加を勧める。
第101問
相談援助における「個人」と「環境」をめぐる諸説に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1. ジャーメイン(Germain,C,)らは,生態学の視点を用いて,個人に焦点化した適応概念について説明した。
2. ホリス(Hol1is,F,)は,パーソナリテイの発達を目指して,個人と社会環境との聞を個別に意識的に調整することについて論じた。
3. パールマン(Perlman,H,)は,役割概念を用いて,役割ネットワークのなかで生成している存在として個人をとらえた。
4. パートレット(Bartlett,H,)は,人間にとってふさわしい場所の質は,その人の願望,能力,自信,環境の資源の機能によって決定されるとした。
5. ゴスチャ(Goscha,R,)らは,社会生活機能の概念を,環境からの要求と個人が試みる対処との交換及び均衡に焦点化してとらえた。
第102問
課題中心アプローチに関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
1. リード(Reid,W,)とエプスタイン(Epstein,L,)によって開発され,心理社会的アプローチ,問題解決アプローチ,行動変容アプローチなどの影響を受けて発達した。
2. ターゲットとなる問題は,クライエントの気付きの有無にかかわらず,クライエントの努力で解決できる可能性があるという基準によって選択される。
3. 様々なアプローチを折衷したものであるので,それらを統合するためにシステム理論をその基礎理論としている。
4. 現在の課題の元となる問題の原因を解明することから援助を始め,その原因の除去を援助の目標とする。
5. 時間的な構造が重要と考え,援助に要する期間を早い段階から定めることを重視し援助を進める。
第103問
ソーシャルワークのアプローチに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
1. 危機介入アプローチは,急性の心理的危機状態にあるクライエントに対して,新しい対処パターンを教示しつつ,長期処遇で対処能力を強化する。
2. 実存主義アプローチは,実存主義思想による概念を用いてクライエントが自らの存在意味を把握し,自己を安定させることで,疎外からの解放を目指す。
3. 行動変容アプローチは,学習理論をソーシャルワーク理論に導入したもので,クライエントのコンピテンスの消去や強化により,問題行動全体の変容を図る。
4. 解決志向アプローチは,社会変草のために,ソーシャルワーカーが解決イメージを提示しながら,解決方法を構築する。
5. フェミニストアプローチは,女性が体験している現実を自ら認識させ,個人が抱える問題の解決を意図した治療的なかかわりを支援の焦点とする。
第104問
事例を読んで, E社会福祉士によるFさんへの援助に関する次の記述のうち,社会生活技能訓練に基づく支援として最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
障害者就労支援事業所のE社会福祉士は,就労後の職場での適応,定着を図るために,共通の課題をもっ知的障害のある若い利用者のグループで社会生活技能訓練を行っている。参加者のFさん(30歳,男性)は清掃作業を行う会社に就職し, 3か月が過ぎたところである。派遣されたビルでの清掃の手順等も覚えて慣れてきたが,同僚や上司,派遣先の人とどう接していいのか分からず,疎外感をもち大変悩んでいた。このままでは人間関係が苦痛で仕事に行けなくなるという不安や,挨拶が大変苦手でありそれを克服したいという気持ちをもち,社会生活技能訓練を行うこのグループに参加している。
1. Fさんの疎外感や不安感の克服のために,グループで受容しあえるように導く。
2. 上司にグループ活動への参加を依頼し,その場で指導や助言を行ってもらう。
3. 挨拶が実際の場面でうまくできるよう,目標を設定して,練習に取り組む。
4. 清掃技術向上のために技術指導者を派遣し職場での実践的な支援を提供する。
5. Fさんの人間関係の苦痛の緩和のために,できるだけ人と接触しなくて済む方法を考えて,練習する。
解答
第 98問 2
第 99問 4
第100問 4
第101問 3
第102問 1・5
第103問 2
第104問 3
注目の記事
濃縮シリーズ紹介
なんでも百科
社会福祉士とは
- 社会福祉士とは?
- 社会福祉士になるには
- 社会福祉士資格の制度概要
- 社会福祉士の受験資格取得について
- 社会福祉士国家試験合格基準って?
- 社会福祉士のニーズはあるの?
- 社会福祉士の給料ってどのくらい?
- 社会福祉士国家試験の合格率って?
- 社会福祉士の求人状況って?
- 社会福祉士の通信講座って?
- 社会福祉士の通学講座って?
- 社会福祉士って働きながら取得することって可能?
- 社会福祉士になる適性って?
- 社会福祉士の魅力って?
- 社会福祉士の合格発表っていつ?
- 社団法人 日本福祉士会って?
社会福祉士の試験勉強
- 社会福祉士の試験概要って?
- 社会福祉士国家試験出題基準って?
- 人体の構造と機能及び疾病の出題基準(科目別出題基準)
- 心理学理論と心理的支援の出題基準(科目別出題基準)
- 社会理論と社会システムの出題基準(科目別出題基準)
- 現代社会と福祉の出題基準(科目別出題基準)
- 地域福祉の理論と方法の出題基準(科目別出題基準)
- 福祉行財政と福祉計画の出題基準(科目別出題基準)
- 社会保障の出題基準(科目別出題基準)
- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度の出題基準(科目別出題基準)
- 低所得者に対する支援と生活保護制度の出題基準(科目別出題基準)
- 保健医療サービスの出題基準(科目別出題基準)
- 権利擁護と成年後見制度の出題基準(科目別出題基準)
- 社会調査の基礎の出題基準(科目別出題基準)
- 相談援助の基盤と専門職の出題基準(科目別出題基準)
- 相談援助の理論と方法の出題基準(科目別出題基準)
- 福祉サービスの組織と経営の出題基準(科目別出題基準)
- 高齢者に対する支援と介護保険制度の出題基準(科目別出題基準)
- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の出題基準(科目別出題基準)
- 就労支援サービスの出題基準(科目別出題基準)
- 更生保護制度の出題基準(科目別出題基準)