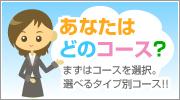濃縮!社会福祉士 無料!過去問特集
「過去問特集」コーナーでは、社会福祉士試験で過去に出題された試験問題と解答を掲載しています。過去問は自分の実力を試す際に、チャレンジすることもできますが、それ以上に「学習をこれから始める!」といった時期に活用するのが非常に効果的です。過去問を見れば、試験の傾向をつかむことができます。社会福祉士の学習を、これから始めようとしている方も、ぜひ一度、過去問を解いてください!
第24回過去問題
権利擁護と成年後見制度
社会福祉士・精神保健福祉士共通科目
第70問
行政処分と行政不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1. 介護保険法における介護保険給付に関する処分や障害者自立支援法における介護給付費等に係る処分に不服がある場合には、都道府県知事に審査請求を行うことができる。
2. 最近の判例によると、生活保護の実施機関が被保護者に対して行う生活の維持,向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示が行政処分に当たることはないとされている。
3. 審査請求に対する裁決はできる限り速やかに行われるべきではあるが、拙速な判断は避けるべきであるから、介護保険法,障害者自立支援法,生活保護法などの社会保障立法には裁決をすべき期間についての定めはない。
4. 介護保険法における介護保険給付に関する処分や障害者自立支援法における介護給付費等に係る処分の取消しを求める訴訟は、原則として審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起できない。
5. 介護保険法や障害者自立支援法における審査請求は、文書で行わなければ受理されない。
第71問
事例を読んで、Jさんの具体的な相続分に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
〔事例〕
被相続人Hさんは、唯一の財産である現金4,000万円を遺して死亡した。Hさんの相続人は、いずれもHさんの嫡出子であるJさん,Kさん,Lさん,Mさんの4名である。Jさんは、結婚したときにHさんから1,000万円の生前贈与を受けているが、Hさんが死亡した時点では500万円しか残っていなかった。また、Hさんは、相続財産のなかから、知人Nさんに1,000万円遺贈する旨の遺言書を作成している。
1. Jさんは、何ら取得できない。
2. Jさんは、875万円を取得する。
3. Jさんは、750万円を取得する。
4. Jさんは、1,000万円を取得する。
5. Jさんは、500万円を返還しなければならない。
第72問
事例を読んで、不法行為と損害賠償責任に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
〔事例〕
訪問介建事業者P法人の正職員であるA訪問介護員が、食事の準備ができたので、利用者Bさんをベッドのある居室から食卓のある居間に車いすで移動させたとき、利用者Bさんが転倒・骨折した。
1. P法人は、転倒,骨折が不可抗力であったとしでも不法行為責任を負う。
2. P法人は、A訪問介護員に故意又は過失があれば不法行為責任を負う。
3. P法人がBさんとの契約で、A訪問介護員の故意又は過失を問わず一切の不法行為責任を免れると定めることは有効である。
4. P法人がBさんとの契約で、A訪問介護員に故意がある場合にのみ不法行為責任を負うと定めることは有効である。
5. Bさんは、A訪問介護員の故意又は過失を理由として、A訪問介護員の不法行為責任を追及していくことはできない。
第73問
福祉関係事業者における個人情報等の適切な取扱いに関する法令及び「ガイドライン」についての次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1. 福祉関係事業者は、利用者の同意がなければ、急病の場合でも医師に利用者の個人情報を伝えてはならない。
2. Q施設が、個人情報の利用目的として「R施設に入所者の個人情報を提供すること」と公表している場合、R施設への個人情報提供に当たって本人の同意は必要としない。
3. 個人情報取扱事業者に該当しない小規模の社会福祉法人であれば、その職員が第三者に利用者の秘密を漏らしても法令違反とはならない。
4. 個人情報を利用する際にはあらかじめ本人の同意を得ることが原則となるが、成年後見審判等を受けていない知的障害者の個人情報を利用する場合は、家族の同意でよい。
5. 特定のサービス利用者の事例を学会で発表する場合、本人の匿名化が困難なケースでは本人の同意を得なければならない。
(注) 「ガイドライン」とは、「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」(平成16年11月厚生労働省)のことである。
第74問
後見人の責務に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1. 成年後見人は、被後見人の身上に関する事務を遂行するに当たっては、被後見人本人の意思を尊重する義務は負わない。
2. 成年後見人は、不適切な事務遂行行為によって第三者に損害を与えた場合、被後見人に事理弁識能力があるときには、その第三者に対して損害賠償責任を負わない。
3. 未成年後見人は、被後見人に対する事務を遂行するに当たっては、善良な管理者としての注意義務を負う。
4. 成年後見人は、財産のない被後見人に対する事務を遂行するに当たっては、善良な管理者としての注意義務は負わない。
5. 未成年後見人は、被後見人たる児童が同居の親族に該当する場合、未成年後見人が被後見人の財産を横領したとしても刑を免除する親族間の特例が適用される。
第75問
「成年後見関係事件の概況」による成年後見制度の動向に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1. 審理期間を見ると、2か月以内に終点したものが全体の約50%で長期化する傾向にある。
2. 申立人と本人との関係を見ると、検察官の申立は市町村長の申立よりも多い。
3. 家庭裁判所管内別の市町村長申立件数を見ると、東京よりも大阪の方が多い。
4. 本人の男女別割合を見ると、女性よりも男性の方が多い。
5. 本人の10歳ごとの年齢別割合を見ると、男女とも80歳以上(80歳以上のすべての年代を含む)が最も多い。
(注) 「成年後見関係事件の概況」とは、「成年後見関係事件の概況一平成22年1月~12月」(最高裁判所事務総局家庭局)のことである。
第76問
事例を読んで、次の記述のうち、施設から相談を受けた地域包括支援センターの社会福祉士の提案として、最も適切なものを一つ選びなさい。
〔事例〕
Cさんは要介護5の重度の認知症高齢者で、2年前から介護老人福祉施設に入所しているが、3か月間利用料を滞納している。Cさんの長男Dさんは、Cさんの老齢基礎年金を管理し、入所契約時の保証人であるが、一度も面会に来ず、利用料支払いの督促にも応答がない。DさんはCさんの次男Eさんと同居しているが、Eさんには中程度の知的障害があり、2級の障害基礎年金を受給し、就労継続支援B型のサービスを利用している。Dさんは1年前に解雇され、継続して求職活動を行ってきたが、現在も無職で、預貯金もないため、Cさん及びEさんの年金で生活している。DさんはEさんの日常生活上の世話をし、Eさんに関する諸費用の支払いに滞納はないなど、DさんとEさんの関係は良好である。
1. 滞納利用料を徴収するため、まずCさんの年金を受ける権利を差し押さえてください。Cさんについては成年後見制度の活用を検討してみましょう。
2. Cさんとの入所契約を解除して、施設からの退所を求めてはどうですか。
3. Eさんを申立人及び後見人等候補者として、Cさんに対する後見開始等の審判請求をするようにEさんに交渉してみましょう。
4. Cさんには成年後見制度の活用を検討し、Dさんには生活保護申請を助言してみましょう。
5. CさんとEさんに成年後見制度の活用を検討し、Eさんの施設入所も相談してみましょう。
解答
第70問 4
第71問 1
第72問 2
第73問 5
第74問 3
第75問 5
第76問 4
注目の記事
濃縮シリーズ紹介
なんでも百科
社会福祉士とは
- 社会福祉士とは?
- 社会福祉士になるには
- 社会福祉士資格の制度概要
- 社会福祉士の受験資格取得について
- 社会福祉士国家試験合格基準って?
- 社会福祉士のニーズはあるの?
- 社会福祉士の給料ってどのくらい?
- 社会福祉士国家試験の合格率って?
- 社会福祉士の求人状況って?
- 社会福祉士の通信講座って?
- 社会福祉士の通学講座って?
- 社会福祉士って働きながら取得することって可能?
- 社会福祉士になる適性って?
- 社会福祉士の魅力って?
- 社会福祉士の合格発表っていつ?
- 社団法人 日本福祉士会って?
社会福祉士の試験勉強
- 社会福祉士の試験概要って?
- 社会福祉士国家試験出題基準って?
- 人体の構造と機能及び疾病の出題基準(科目別出題基準)
- 心理学理論と心理的支援の出題基準(科目別出題基準)
- 社会理論と社会システムの出題基準(科目別出題基準)
- 現代社会と福祉の出題基準(科目別出題基準)
- 地域福祉の理論と方法の出題基準(科目別出題基準)
- 福祉行財政と福祉計画の出題基準(科目別出題基準)
- 社会保障の出題基準(科目別出題基準)
- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度の出題基準(科目別出題基準)
- 低所得者に対する支援と生活保護制度の出題基準(科目別出題基準)
- 保健医療サービスの出題基準(科目別出題基準)
- 権利擁護と成年後見制度の出題基準(科目別出題基準)
- 社会調査の基礎の出題基準(科目別出題基準)
- 相談援助の基盤と専門職の出題基準(科目別出題基準)
- 相談援助の理論と方法の出題基準(科目別出題基準)
- 福祉サービスの組織と経営の出題基準(科目別出題基準)
- 高齢者に対する支援と介護保険制度の出題基準(科目別出題基準)
- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の出題基準(科目別出題基準)
- 就労支援サービスの出題基準(科目別出題基準)
- 更生保護制度の出題基準(科目別出題基準)