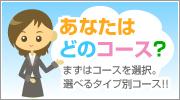濃縮!社会福祉士 無料!過去問特集
「過去問特集」コーナーでは、社会福祉士試験で過去に出題された試験問題と解答を掲載しています。過去問は自分の実力を試す際に、チャレンジすることもできますが、それ以上に「学習をこれから始める!」といった時期に活用するのが非常に効果的です。過去問を見れば、試験の傾向をつかむことができます。社会福祉士の学習を、これから始めようとしている方も、ぜひ一度、過去問を解いてください!
第24回過去問題
相談援助の理論と方法③
専門科目
第105問
地域包括支援センターに勤務するJ社会福祉士は、地区の民生委員から、「近所に住むKさんのことなのですが、70代後半の女性で一人暮らしをしています。最近、どうも様子がおかしく、季節にそぐわない服装で出歩き、足元もおぼつかなくなっています。少し痩せてきているようにも見えます。また、家の周りにはごみが散乱して悪臭がただよい、近隣住民からの苦情が増えています。私も何度か訪ねているのですが、いつもすごい剣幕で「用はない、帰れ!」の一点張りです。何か良い方法がないものでしょうか」と相談を受けた。民生委員から相談を受けた後、すぐさま、J社会福祉士はKさん宅を訪問したが、その日はKさんに拒否されて会うことができなかった。 次のうち、この時点でのJ社会福祉士の対応として、最も適切なものを一つ選びなさい。
1. 玄関に名刺やKさん宛のメモを置いて、Kさん宅への訪問を継続する。
2. 民生委員に今後の対応をゆだね、状況に変化があった際の報告を依頼する。
3. Kさん宅に電話を入れ、センターに来所するよう伝える。
4. 民生委員と協力して、Kさん宅のごみの片付けを行う。
5. Kさんの意向を尊重し、センターに連絡があるのを待つ。
第106問
事例を読んで、L相談支援専門員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。
〔事例〕
相談支援事業所のL相談支援専門員は、中程度の高次脳機能障害をもつMさん(34歳男性)の父親から、「これからどうしていったら良いのでしょうか、先行きが全く見えません。息子は毎日、目的なくただ過ごしています。いったい何をしているんでしょうか。一日も早く自立してもらいたいです」と相談を受けた。これまでMさんは、父親の友人から紹介された職場で何度か就労を経験しているが、長続きしなかった。また、地域活動支援センターの利用は、父親がやめさせている。最近のMさんは、毎日、地域の公民館のロビーに行って過ごし、夕方になり帰宅するという生活で、その状態が半年以上続いているとのことである。
1. Mさんの気持ちを確認の上、Mさんの考えを伝えるために父親に三者面接を提案する。
2. 父親の考えを尊重し、Mさんと個別面談を行い就労自立に向けた努力をするよう助言する。
3. 日中活動の場が必要なため、Mさんと個別面接を行い作業所への適所を勧める。
4. Mさんと個別面接を行い、父親の気持ちを代弁してこれ以上心配をかけないように伝える。
5. 就労先確保のため、障害者の雇用経験をもつ事業所に関する情報を父親に提供する。
第107問
ソーシャルサポートネットワークを活用した支援に関する次の記述のうち、適切なものを一つ選びなさい。
1. インフォーマルなサポートよりもフォーマルなサービスの機能に着目し、それを活性化しようとするものである。
2. 第一義的な目的は、ソーシャルサポートを提供する組織間のつながりを強めて、効果的に連携できるようにすることである。
3. ソーシャルサポートネットワークをアセスメントする場合は、利用者の主観的な意見にとらわれず、客観的にとらえる。
4. ソーシャルサポートネットワーク形成の方法として、自然発生的ネットワーク内に関与する場合と、新しい結びつきをつくる場合がある。
5. ソーシャルサポートの機能は、個人の情緒的支援をするのではなく、政策レベルでのサポートを実現しようとするものである。
第108問
事例を読んで、就労継続支援事業所のN生活支援員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。
〔事例〕
N生活支援員は、18歳から20歳代前半の知的障害のある利用者6人(いずれも男性)によるグループを新たに形成して、メンバーの自己表現力や生活意欲の向上を目的とするグループワークを実施してきた。彼らは、この事業所に通所するようになって、まだ日が浅いメンバーたちであった。また、共通して自己表現力が乏しい上に、親や援助者への依存的な傾向が敢く、生活意欲も低い傾向がみられた。N生活支援員は、週に1度の余暇活動の時間を利用してグループ活動を行うことにして、1時間程度のメンバーによる話合いを中心としたプログラムを実施してきた。
1. メンバーの依存的な傾向を考え、自主的な話し合いがなされるまで待ち続けた。
2. 最も資質のあると思われる一人のメンバーを、グループのリーダーに指名した。
3. 遅刻者や発言しないメンバーがいたので、そういう態度ではグループ活動に参加させられないことを伝えた。
4. メンバー間の言い争いが生じた場面で、メンバー同士がお互いに話し合って解決していくことを促した。
5. 仲の良い3人のメンバーからなる下位グループが形成されたので、3人に対してお互いに距離を置くように指示した。
第109問
スーパービジョンに関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1. 個人スーパービジョンとは、複数のスーパーバイザーが、一人の援助者に対してスーパービジョンを行うことをいう。
2. グループスーパービジョンとは、複数のスーパーバイザー間の相互作用を活用しながら、援助者に対してスーパービジョンを行うことをいう。
3. セルフスーパービジョンとは、援助者が所属する職場内の人間関係を、援助者自らが活用してスーパービジョンを行うことをいう。
4. ピアスーパービジョンとは、援助者が所属する職場内の上下関係を活用してスーパービジョンを行うことをいう。
5. ライブスーパービジョンとは、スーパーバイザーが援助者の実践場面に同席するなどしてスーパービジョンを行うことをいう。
第110問
「個人情報の保護に関する法律」又は「福祉関係事業者における個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」(厚生労働省)に関する次の記述のうち、正しいものを一つ選びなさい。
1. 事業者がサービス利用者から本人のサービス利用の情報提供を求められた場合には、書面による手続きを求め、情報提供の可否について慎重な審査を行い対応しなければならない。
2. 福祉関係事業者は、プライバシーポリシーを策定,公表して、利用者等の理解を得るとともに、法を遵守し、個人情報保護の積極的な取組の姿勢を対外的に示すことが求められる。
3. 死亡した個人の情報については、その情報が遺族等の生存する個人に関連するものである場合においても、法律やガイドラインの対象外となる。
4. サービス利用者やその家族に関する個人情報は法律の対象に含まれるが、施設の職員やボランティアに関する個人情報は対象から除かれる。
5. 個人情報の利用にはあらかじめ本人の同意が必要であり、児童虐待事例について関係機関と情報交換する場合も同様である。
第111問
事例を読んで、A生活支援員(社会福祉士)が開催するケースカンファレンスに関する次の記述のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。
〔事例〕
就労継続支援事業所に最近通い始めた知的障害のあるBさん(28歳,男性)は、ここ1週間ほど作業に集中できなくなり、急に席を立って歩き回ることが多く、他の利用者に暴力をふるうこともあった。担当のC職員は、このようなBさんの行動の原因が分からないまま対応に悩んでおり、上司で主任のA生活支援員に相談した。相談を受けたA生活支援員は、Bさんのことを取り上げるケースカンファレンスを開催することにした。
1. Bさんの暴力行為を鎮めるための対応の仕方に焦点を当てて、話し合いを行う。
2. Bさんの本事業所の利用は難しいと判断して、他の事業所を利用することを検討する。
3. Bさんの行動に関する情報や考えを参加者で出し合って、その要因を探る。
4. 事業所内でのBさんの担当職員を変更し、A生活支援員自らが担当することをその場で通知する。
5. C職員に生育歴を開いて自己覚知を促し、Bさんに対するC職員の対応の仕方を見直す機会とする。
解答
第105問 1
第106問 1
第107問 4
第108問 4
第109問 5
第110問 2
第111問 3
注目の記事
濃縮シリーズ紹介
なんでも百科
社会福祉士とは
- 社会福祉士とは?
- 社会福祉士になるには
- 社会福祉士資格の制度概要
- 社会福祉士の受験資格取得について
- 社会福祉士国家試験合格基準って?
- 社会福祉士のニーズはあるの?
- 社会福祉士の給料ってどのくらい?
- 社会福祉士国家試験の合格率って?
- 社会福祉士の求人状況って?
- 社会福祉士の通信講座って?
- 社会福祉士の通学講座って?
- 社会福祉士って働きながら取得することって可能?
- 社会福祉士になる適性って?
- 社会福祉士の魅力って?
- 社会福祉士の合格発表っていつ?
- 社団法人 日本福祉士会って?
社会福祉士の試験勉強
- 社会福祉士の試験概要って?
- 社会福祉士国家試験出題基準って?
- 人体の構造と機能及び疾病の出題基準(科目別出題基準)
- 心理学理論と心理的支援の出題基準(科目別出題基準)
- 社会理論と社会システムの出題基準(科目別出題基準)
- 現代社会と福祉の出題基準(科目別出題基準)
- 地域福祉の理論と方法の出題基準(科目別出題基準)
- 福祉行財政と福祉計画の出題基準(科目別出題基準)
- 社会保障の出題基準(科目別出題基準)
- 障害者に対する支援と障害者自立支援制度の出題基準(科目別出題基準)
- 低所得者に対する支援と生活保護制度の出題基準(科目別出題基準)
- 保健医療サービスの出題基準(科目別出題基準)
- 権利擁護と成年後見制度の出題基準(科目別出題基準)
- 社会調査の基礎の出題基準(科目別出題基準)
- 相談援助の基盤と専門職の出題基準(科目別出題基準)
- 相談援助の理論と方法の出題基準(科目別出題基準)
- 福祉サービスの組織と経営の出題基準(科目別出題基準)
- 高齢者に対する支援と介護保険制度の出題基準(科目別出題基準)
- 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度の出題基準(科目別出題基準)
- 就労支援サービスの出題基準(科目別出題基準)
- 更生保護制度の出題基準(科目別出題基準)